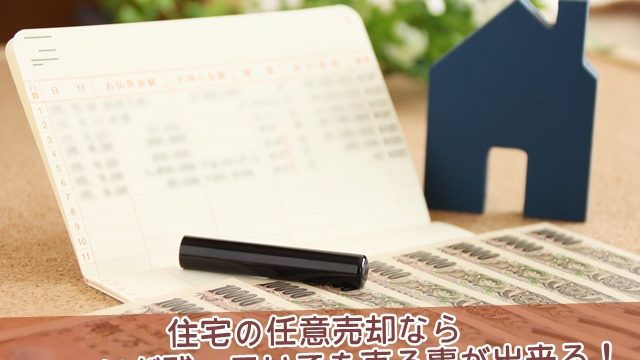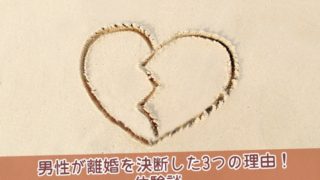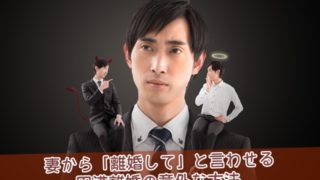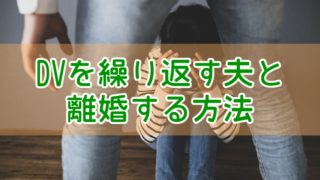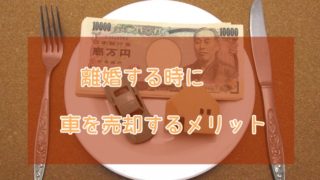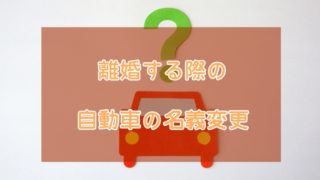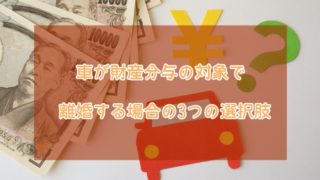住宅における財産分与の基本的なルールとその理由
夫婦が離婚する時、二人の財産をどう分けるかは難しい問題です。
法律的にいうと基本的に、
- 結婚後に二人で手に入れた財産は二人で分ける
- 結婚前に個々に手に入れていた財産は個人のもの
- 名義いかんに関わらず実質的な分け方をする
という決まりがあります。
しかし、住宅やマンションなどの不動産は高価なだけに「誰がいくら出して買ったか」が複雑です。
離婚時の財産分け(財産分与)では、この「誰がいくら出したか」が重要になるので複雑であればあるほど分け方が難しくなってしまうのです。
住宅を分ける時の基本的なルール
住宅(一戸建て・マンション等)を財産分与するにはルールがあります。
そのルールの基本となるのは、「購入時に誰がいくら出したか」や「ローンを払っている割合」などです。
たとえば住宅購入当時の価格が3000万円としましょう。
うち「頭金1000万円を夫の親」、「残り2000万円を夫と妻が50%ずつ」と負担したとします。
この場合は、住宅の3分の2の権利を夫、3分の1権利を妻が持っています。
そこで現在の住宅の時価が1500万円であれば、「1000万円分を夫」「500万円分を妻」の権利となるわけです。
上記はごくごくシンプルなケースで、一般的には住宅ローンの支払い中であったりするなど問題は複雑でしょう。
住宅ローン支払い中の場合は、夫と妻がどのくらいの割合でローンを負担しているかも分与割合に関わってきますので単純には割り切れません。
まずは、離婚時の住宅の財産分与は、「夫と妻・各自の負担した割合で権利が違ってくる」と覚えておくといいでしょう。
もちろん、こうした割合に細かくこだわらず、夫婦の話合いで問題を解決するという方法もあります。
離婚時の財産分与が複雑な理由
夫婦が離婚する場合、二人の財産を分けるというのが一般的です。
いったん離婚すれば「夫婦といえども赤の他人」になるわけですから、これまで共にしてきた財産も分ける(分与する)のが当たり前といえば当たり前でしょう。
ところが離婚時の財産分与には、一般の人には分かりにくい法的な解釈があります。
これは何も財産分与を複雑にしようとして定められたものというわけではなく、夫婦が赤の他人になる際に不公平にならないようにと公平を期して定められたものです。
しかし、いくら公平を期しているといっても、法律で定められたものには限界があります。
離婚時の財産分与で揉めて離婚がスムーズに進まなかったり、離婚回避できそうなのに揉めた事によって夫婦仲の亀裂が決定的になるようでは意味がありません。
財産分与の仕方は人それぞれ、夫婦の考え方一つで揉めずに解決する事も可能なのです。
財産分与には「共有財産」「特有財産」「実質的共有財産」の3種類がある
夫婦離婚で財産分けをする際、基本となるのは「婚姻生活で築いた財産を分与する」という決まりです。
婚姻生活で築いた財産は「共有財産」といい、簡単にいうと「結婚してから夫婦で協力して手に入れた財産」という事になります。
たとえば、結婚してから夫婦で相談して購入したソファとかオーディオといったアイテム、二人で協力して蓄えた預貯金などがあり、もちろん夫婦で購入したマイホームもそれに該当します。
一方、夫婦の財産の中には離婚時でも分与する必要のない財産もあります。
こうした財産は「特有財産」といい、結婚前に蓄えた貯金や自分の両親から相続した不動産などが含まれます。
さらに、この2種類の財産に含まれない「実質的共有財産」という種別もあり、法律に詳しくない人からすると少々分かり難いかもしれません。
次に離婚時に住宅はどの種別に含まれるのかなど、離婚に際して知っておきたい3つの財産分与の種類について説明していきましょう。
夫婦で分ける「共有財産」
離婚時に夫婦で分ける財産分与の対象となるのが「共有財産」です。
「共有財産」は結婚後に夫婦が二人で協力し、合意の上で取得した財産を指します。
結婚後、もしくは結婚準備の為に二人で相談し、協力して費用を出し合って購入した住宅などは財産分与の対象となります。
ただし、住宅購入の際に夫婦いずれかの両親が頭金を出していたり、夫婦のどちらかが結婚前の預金を支払いに使っているなどの条件によって分与方法は違ってきます。
夫婦で分けない「特有財産」
離婚時に問題となる「特有財産」とは、夫婦が結婚前に独自に得ていた財産を指します。
たとえば結婚前に個人で購入した住宅やマンション、両親から相続した住宅などは「特有財産」に含まれます。
こうした「特有財産」は離婚に当たっても夫婦二人で分ける必要はなく、もともとの所有者であった夫(妻)個人の財産と解釈されます。
つまり離婚する場合でも夫婦で分ける「共有財産」には含まれないという事です。
夫婦で分ける「実質的共有財産」
夫婦の財産分与対象となる「共有財産」に「実質的」という言葉が付いています。
これは名義が夫婦いずれかのものになってはいるものの、実質的には夫婦の共有財産であるという種別です。
代表例としては貯金や貯蓄型生命保険などが該当しますが、住宅やマンションが夫婦片方の名義になっていても実質的には共有財産とみなされ財産分与の対象となります。
以上、ここまで離婚時の夫婦の財産分与の種別について説明してきましたが、現実には法律的な問題となりますので個々のケースによって解釈は異なってきます。
どの財産がどの種別に当てはまるかは、個々にしっかりと確認しましょう。
離婚したら共有財産の家はどうなる?

一般的には、エアコンや冷蔵庫などの家庭用電気製品、タンスや食器棚などの家具・調度品、家族で使用する乗用車といったものが共有財産となります。
夫婦離婚する際、エアコンや食器棚をどちらが貰うかで喧嘩になる事は少ないでしょうが、それがマイホーム(家・住宅・マンション・土地・建物=不動産)となると厄介な問題が発生します。
離婚したら家はどうなる?
夫婦が離婚したらマイホームがどうなるのかは入手経緯によって異なります。
離婚で財産分与(財産分け)しなければならないのは「共有財産」で、結婚前から所有していた貯金や親から相続した住宅などは含まれません。
そこで夫婦で住んでいるマイホームといえども、夫または妻が個人で取得したり親から譲られたものであれば財産分けする必要は無いわけです。
仮にマイホームが「夫が自分の親から相続したもの」であれば、ほとんどのケースで妻には何の権利もなく「そのまま夫のもの」になります。
逆に妻の実家に夫婦で住んでいて、妻の両親が死亡して「妻が相続した家」であれば、ほとんどのケースで「そのまま妻のもの」になるのです。
ところが、夫婦が力を合わせて購入したマイホームですと、離婚する際には「夫婦の財産分けの対象」となります。
住宅の財産分与の分け方
離婚の財産分与といっても、マイホームは「分けるのが困難なもの」の一つです。
その理由は…、
- 夫婦がマイホーム取得に貢献した割合
- 住宅ローンが残っている場合の対処方法
- どちらがマイホームを取得するかの選択
といった問題があるからです。
一例を挙げると、3000万円のマイホームであっても、次のようなケースでは財産分与の仕方が違ってきます。
- 夫が1500万円、妻が1500万円出して購入
- 夫が2000万円、妻が1000万円出して購入
- 妻が2000万円、夫が1000万円出して購入
- 夫の親が1000万円、夫が1000万円、妻が1000万円出して購入
- 妻の親が1000万円、夫が1000万円、妻が1000万円出して購入
というように同じマイホームでも、様々な入手方法があります。
この入手方法の種類によって「離婚時のマイホームという財産の分け方」にも違いが出てくるのです。
4タイプの夫婦から見る住宅(持ち家・マンション)の財産分与例
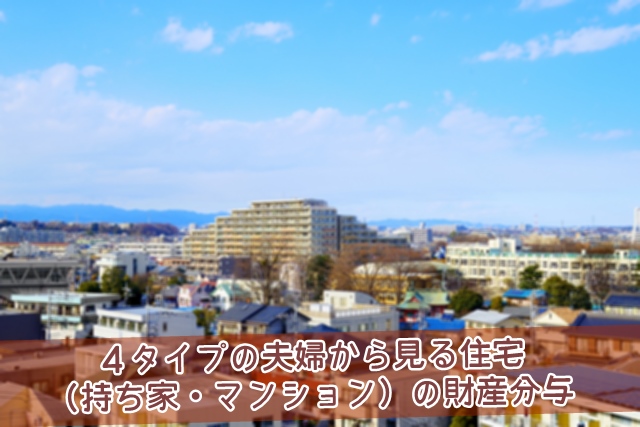
住宅の財産分与の基本ルールは「購入時に誰がいくら出したか」です。加えて、ローンなどがあれば「誰がいくら払ったか」もポイントになります。
例1・夫が相続した家
Aさん夫妻の持ち家は、夫であるAさんが両親から相続したものです。
離婚時の財産分与の対象にはならず、持ち家は夫であるAさんのものになります。
これは妻であるA子さんが両親から相続した場合も同様で、持ち家はA子さんの個人的な財産(特有財産)とみなされ財産分与の対象にはなりません。
例2・夫婦二人で買った家
Bさん夫妻が住む分譲マンションは、結婚後に二人が協力して家計から資金を出して購入したものです。
この場合は夫婦の寄与分・貢献度は50%ずつとなり、離婚時の財産分与でも50%ずつの分配で分けるという事になります。
もちろん不動産はそのままでは分ける事ができませんので、売却して現金で分けるか、夫婦の一方が権利を得て分与に当たる相当額を一方に支払うといった方法を取る事になるでしょう。
例3・親が頭金を出した家
Cさん夫妻が住む一戸建て住宅は、結婚時に妻であるC子さんの両親が頭金を払って購入したものです。
頭金の残金は夫婦が協力して家計からローンを支払って完済しています。
この場合は、頭金の分はC子さんの特有財産とみなされ、残りのローンを支払った分を夫婦二人で分与する事になります。
例4・夫婦でローンを払った家
Dさん夫妻が住む住宅は、夫婦二人で頭金とローンを払って購入したものです。
頭金は夫婦共に50%ずつ支払い、ローンは家計から捻出しています。
この場合は基本的に「住宅の権利は夫婦50%ずつ」となりますが、支払いに当たって夫婦いずれかの寄与度が低い場合は50%ずつ分けるとならないケースもあります。
たとえば妻が専業主婦で収入がないケースでは、妻の住宅に対する寄与度は30~40%と判断される事もあります。
その結果、住宅に関する夫の権利は60~70%となり、財産分与でもその割合で分ける事になるでしょう。
離婚で「家はどうする?」の厄介なポイント

離婚で家に関する厄介ポイントとしては、
- 家は夫と妻のどちらが財産分与で受け取るか
- 家を残すべきか、貸すべきか、売るべきか
- 住宅ローンの残額を誰が支払うべきか
- 家の名義を誰にするか、それは可能か
などが挙げられます。
家は誰のものにすべきか?
これまで夫婦で仲良く暮してきた住宅でも、いざ離婚となればどちらかが出て行かなければなりません。
一般的な家の価値は数百万円から数千万円とかなりの価値がある為、どちらが受け取るにしても差額の支払いなど財産分与のバランスを取るのに苦労するようです。
受け取り後も毎年の固定資産税支払いなどの負担もありますので、どちらが家を自分のものにするかは熟考して決めるようにしてください。
ローン返済中の家は要注意
熟年離婚で「家のローンはほとんど支払済み」というケースは別として、返済期間が20年も30年も残っているようなら家の売却はできない場合があります。
仮に現在の相場で家を売却しても、ローン残金よりも安くて完済が難しいと抵当権が消せないので売却が不可能となりやすいのです。
妻が家に住み続けたい場合
夫名義の家に妻が住み続けるという場合、住宅ローンの支払いの関係で問題が起こる事があります。
離婚前の二人は夫婦なので家の名義が誰であるかはあまり問題ではありませんが、いったん離婚すれば夫婦といえども他人になります。
元妻は他人名義の家に住み続ける事になるわけですが、ローン支払いの責任はローン契約をした人にあります。
夫が契約者なら離婚後も夫がローンの残金を払い続ける必要があります。
離婚で住宅ローン一括払いが必要に
購入した家は夫婦のものと思いがちですが、住宅ローンの支払いが残っているうちは完全に自分たちの所有物とはいえません。
離婚に際しても住宅ローンが残っていると、残金すべてを支払う「一括返済」を求められる場合があります。
銀行やローン会社はローンを組む時の条件(結婚しているなど)と状態が異なると、ローン返済がスムーズにいかなくなると判断する事があるのです。
最後に住宅の財産分与で考えておきたい4つのこと

離婚の財産分与では家を売却すべき?
夫婦離婚で財産分けの話合いがスムーズに進んでいるなら無理に家を売却する必要はありません。
しかし、家の資産価値が高く分けにくいといった場合や住宅ローンの残額支払いで揉めるような場合は家を売却してスッキリ分けるという方法がベターです。
住宅を売却した方がいいのは、家の売却価格がローン残高を上回っているケースです。
もし売却価格よりもローン残金の方が多ければオーバーローンとなって負債を背負う事になります。
オーバーローンの住宅を売却するにはいったんローン残額を一括返金するなどの方法を求められる事になり負担が大きくなります。
離婚後でも住宅に夫(妻)が住み続けられるのか?
離婚しても住宅に住み続けるというケースでは、「家の名義人が誰なのか」という事が問題になります。
名義人である夫(妻)が住み続ける場合は大きな問題はありません。
一方、名義人ではない夫(妻)が住み続ける場合は名義変更をしないとトラブルの原因になります。
また、家の住宅ローンが残っている場合は、住宅の名義人以外に「ローンの名義人が誰なのか」が問題となります。
金融機関はローンの名義人が家に住む事を前提として契約していますので、名義人以外の人が家に住むとなるとクレームが出る場合が多いのです。
住宅とローンの名義人を変更できるのか?
住宅にローン残額がない場合、家の名義人を変更するのに問題はありません。
しかし、ローンが残っている住宅の場合は簡単に名義人を変更する事ができない場合がほとんどです。
住宅ローンを借りる為には金融機関との契約が必要ですが、その契約内容によっては簡単に名義人を変える事ができません。
こうした契約では「名義人が住宅に住む事」や「名義人がローンを完済する事」という内容になっている事が多く、金融機関の承諾なしでは条件を変更する事ができないのです。

財産分与の関係でどうしても家を売りたいが?
離婚の財産分けの際、夫婦の話合いで合意があれば住宅を売る事ができます。
ただし、住宅ローンが残っている家の場合はローン契約をしている金融機関の承諾がなければ家を売る事はできません。
どうしても家を売りたければ、住宅ローンの残額を一括返済するなどの方法を採る必要があります。
一括返済はできないが家を売りたいという場合は任意売却という方法で売る事になります。
任意売却とは不動産業者に債権者(ローン契約をしている金融機関)との調整を仲介して貰い、その上で住宅を売却するという方法です。
この任意売却という方法ではオーバーローンとなった住宅でも不動産市場の相場に近い価格で住宅を売りやすいというメリットがあります。

|
離婚にて持ち家をどうするかでお悩みの方
⇒離婚時の住宅問題を解決するには? |
|
離婚しても家を残す方法
⇒離婚しても家は手放したくない!賃貸するという方法! |